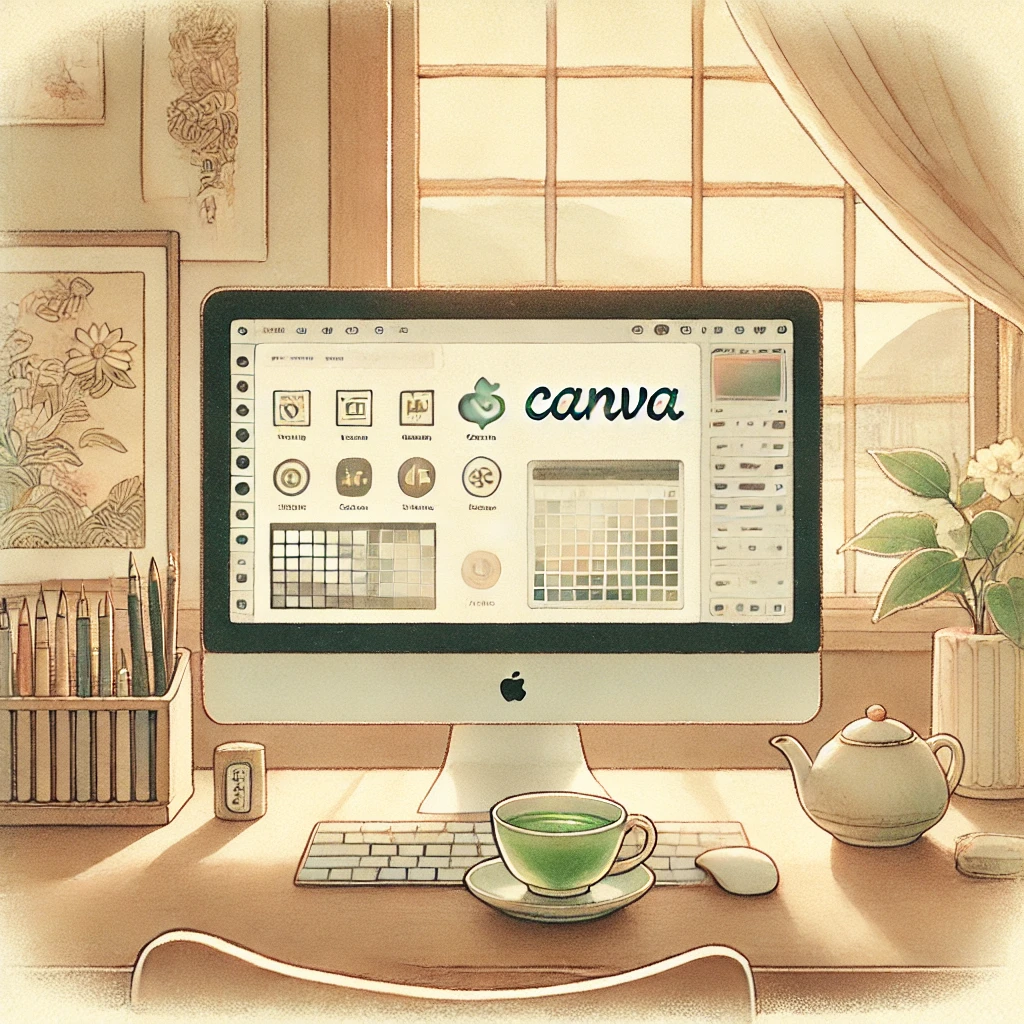DEEP RESEARCHで10年後の中小企業家同友会の会員推移をAIに調べてもらいました
↑ 解説動画はこちら
ChatGPT o3 mini 「詳細な調査」
日本の経営者団体である中小企業家同友会が2035年に向かってどのような会員数になるのか?また他の主要な経営者団体と比較して10年前の2015年と現在と10年後の未来でどんな推移をたどるのか、その要因を各団体の特徴から見出してください。
以下、ChatGPT DEEP RESEARCHのコピー
各団体の会員数推移と要因分析
会員数の推移概要
以下の表に、質問対象となっている主要団体の会員数推移(2015年、2025年(現在)、2035年予測)をまとめます。
| 団体名 | 2015年頃の会員数 | 2025年頃の会員数(現在) | 2035年の会員数(予測) |
|---|---|---|---|
| 中小企業家同友会(全国協議会) | 約4.4万名(2014年時点4万3571名) () | 約4.7万名(2023年時点4万7453名) (知られていない中小企業の真相と中小企業家同友会) | 約5.5万名程度 (緩やかな増加を想定) |
| 日本商工会議所青年部(日本YEG) | 約3.15万名(2015年時点、日本YEG加盟) (YEG27年度調査 OB会頭104人 総会員数3万人突破 |日商 Assist Biz) | 約3.24万名(2023年時点) ([〖6月23日(金)放送〗ラジオ番組 青木仁志のトップリーダーと語る「成功の技術」、日本商工会議所青年部会長の木村麻子さんがゲストで登場! | アチーブメント株式会社のプレスリリース](リンク)) |
| BNIジャパン(国内) | 約0.7万名(2015年9月時点) ([BNI Japan – 会社概要 | Japanese](bniデータ)) | 約1.3万名(2023年7月時点1万2921名) ([1,000名の子供たちが夢をカタチに BNIが子供たちを対象にしたワークショップを実施 |
| ニーズマッチ | 数百名規模(2015年前後、創設直後) | 約1000~2000名規模(2021年時点1026名 ([沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ](https://nm2014.jp/20160104web/news/#:~:text=10%E6%9C%8831%E6%97%A5))。その後拡大) |
注: ニーズマッチの数値は公式公開データが乏しく推定を含みます。また、日本YEGの会員数は日本YEG加盟の青年部のみを指し、未加盟青年部を含む総計はさらに多い(2015年時点約3.44万人、2021年時点約3.56万人) (YEG27年度調査 OB会頭104人 総会員数3万人突破 |日商 Assist Biz) (日本YEG 415カ所3万2552人に 21年度青年部の現状 |日商 Assist Biz)とされています。2035年予測は過去の傾向に基づく仮定です。
以下、各団体ごとに特徴と会員数増減の要因、競合環境やビジネスモデル変化の影響について詳しく分析します。
中小企業家同友会の動向と要因
概要と会員数推移: 中小企業家同友会(中同協)は、中小企業経営者の自主的な学びと連帯を目的とした全国組織です。会員数は長年増加基調にあり、2010年代半ばに会勢4万人を突破、2016年初頭には全国で過去最高の4万5556名を記録しました (静岡同友会が1000名会員達成~企業と同友会の更なる発展を – 中小企業家同友会全国協議会)。2014年時点で約4万3571名 ()、2015年前後には4万4~5万人規模に達し、以降も拡大を続けています。実際、2014年度および2015年度には各年で1000名以上の純増を達成し、2017年時点で約4万6000名に達しました (連載第1回〖2019年5万名達成を〗 地域の隅々に同友会理念を広げよう – 中小企業家同友会全国協議会)。その後も2019年まで11年連続で過去最高を更新し、コロナ禍直前には5万人に迫る勢いでした (4万5000人超…なぜこの経営者団体は会員が増え続けるのか | ゴールドオンライン)。しかし2020年に新型コロナの影響で一時的に純減(約1830名減)となったものの (〖2023組織強化・会員増強全国交流会 問題提起〗組織全体の質と量を高め、仲間づくりを進めよう全国の組織強化・会員増強の課題と今後の仲間づくり 中同協幹事長 中山英敬氏 – 中小企業家同友会全国協議会)、2021年以降は増加基調に回復し、2023年11月時点で会員数は4万7453名(前年比+1000名)と過去最高水準にほぼ並んでいます (知られていない中小企業の真相と中小企業家同友会)。**現在(2025年)**も約4万7千~4万8千名規模と推定されます。将来予測(2035年): このまま緩やかな増加が続けば、2035年には5万5千名前後に達する可能性があります。ただし大幅な伸びには限界もあり、成長が停滞すれば5万前後で横ばいになるシナリオも考えられます。
成長要因: 会員増加の背景には、同友会の組織的な増強活動と魅力向上があります。同友会では「全会員で経営を学ぶ」「地域を変える」という理念の下、新支部の設立や青年経営者・女性経営者の交流会などを全国展開し、会員拡大に努めてきました (連載第1回〖2019年5万名達成を〗 地域の隅々に同友会理念を広げよう – 中小企業家同友会全国協議会)。特に2010年代は新たな支部・地区の立ち上げが各地で相次ぎ、これが会員増強に大きく寄与しました (連載第1回〖2019年5万名達成を〗 地域の隅々に同友会理念を広げよう – 中小企業家同友会全国協議会)。また、同友会が掲げる「自主・民主・連帯の精神」や「社員はパートナー」という労使見解に基づく経営指針づくりなど、経営者の学びの場としての価値が認知されたことも継続的な増加要因です。同友会は経営改善や社員との関係構築に役立つ実践知を共有する場であり、この「経営者団体として類を見ない」独自性が多くの中小企業経営者を引き付けています (4万5000人超…なぜこの経営者団体は会員が増え続けるのか | ゴールドオンライン)。さらに、中小企業の政策提言団体としての側面(例:税制改正への働きかけ等)もあり、中小企業の代表プラットフォームとして社会的影響力を高めたいという経営者層の支持を得ていることも増加の一因です (4万5000人超…なぜこの経営者団体は会員が増え続けるのか | ゴールドオンライン)。実際、会勢拡大により対中小企業組織率10%を目指す動きもあり(現在約3%)、5万人突破はその足がかりと位置付けられました (4万5000人超…なぜこの経営者団体は会員が増え続けるのか | ゴールドオンライン)。
減少要因・課題: 大局的には増加傾向の同友会ですが、課題として会員の高齢化や地域差が挙げられます。既存会員の多くが中高年層であるため、世代交代期には退会も増え得ます。実際コロナ禍では活動停滞もあり2020年度に退会者が新規を上回り会員数が減少しました (〖2023組織強化・会員増強全国交流会 問題提起〗組織全体の質と量を高め、仲間づくりを進めよう全国の組織強化・会員増強の課題と今後の仲間づくり 中同協幹事長 中山英敬氏 – 中小企業家同友会全国協議会)。また主要都市圏では比較的順調に増えても、地方によっては伸び悩みや退会増が課題となる場合もあります。同友会は任意団体で加入・脱退が自由なため、景気動向や経営者の意識変化によっては増減がぶれる可能性があります。特にリーマンショック級の不況や経営者の世代交代期には退会増加のリスクがあります。今後は若手経営者の参加促進や魅力ある活動内容の継続がなければ、成長鈍化・停滞も起こりうるでしょう。
競争環境・ビジネスモデルの影響: 中小企業家同友会は国内で独特のポジションを占めており、直接的な競合団体は少ないと言えます。他の中小企業団体としては商工会・商工会議所や青年会議所(JCI)などがありますが、同友会ほど経営指針の共有や政策提言に軸足を置いた組織はありません。むしろ補完的関係で、同友会会員が商工会議所の会員や青年部員でもあるケースもあります。そのため競合環境よりも、社会環境の変化(例えば中小企業数の減少や経営者の高齢化)による影響の方が大きいでしょう。またビジネスモデルとしては非営利型の会員組織であり、会費収入を元に自主運営されています。オンライン化など環境変化にも対応しており、コロナ禍でも「活動を止めない」としてZOOM会議等を活用し会員交流を継続しました (4万5000人超…なぜこの経営者団体は会員が増え続けるのか | ゴールドオンライン)。こうした柔軟な対応力は会員離れを防ぐ効果があり、結果としてコロナ禍後の会勢回復につながりました。同友会にとって今後のポイントは、デジタル時代の経営者ニーズにどう応えるかです。オンラインコミュニティの台頭や若手経営者の志向性変化に合わせて、研修プログラムの刷新や他団体との連携(例えば大学や専門機関との協業による経営支援など)を進めることで、引き続き組織価値を高められるでしょう。
日本商工会議所青年部(日本YEG)の動向と要因
概要と会員数推移: 日本商工会議所青年部(日本YEG)は、各地商工会議所の青年部(原則45歳以下の若手経営者・後継者らで構成)の全国連合体です。1983年に全国組織化されて以来拡大を続け、2015年時点で日本YEGに加盟する青年部数は409箇所、会員数は約3万1505人(未加盟の商工会議所青年部も含めた全国総計では約3万4425人)に達し、初めて「総会員数3万人突破」と報じられました (YEG27年度調査 OB会頭104人 総会員数3万人突破 |日商 Assist Biz)。その後も加盟青年部は増え、2019年度には加盟会員数約3万4000人に達しています。しかし直近ではやや伸び悩み、現在(2023~2025年)は日本YEG会員数約3万2400人 (〖6月23日(金)放送〗ラジオ番組 青木仁志のトップリーダーと語る「成功の技術」、日本商工会議所青年部会長の木村麻子さんがゲストで登場! | アチーブメント株式会社のプレスリリース)、全国の商工会議所青年部総計で約3万5586人と、2019年比で微減傾向となっています (日本YEG 415カ所3万2552人に 21年度青年部の現状 |日商 Assist Biz)。これはコロナ禍で活動縮小や新規減少があった影響で、2019年から2021年に約1449人減少したためです (日本YEG 415カ所3万2552人に 21年度青年部の現状 |日商 Assist Biz)。将来予測(2035年): 商工会議所青年部の会員数は今後大きな急増は見込みにくく、むしろ少子高齢化や後継者不足の影響で減少圧力が高まる可能性があります。各地の商工会議所の設置率(現在約80~90%)はすでに高水準で新設余地が小さいことから、2035年には日本YEG加盟の会員数で約3万人前後、全国総計でも3万数千人程度と横ばい~微減の推移を予想します。
成長要因: 過去の会員拡大を支えたのは、組織カバー率の拡大と地域経済での存在感向上です。1990年代以降、各地の商工会議所に青年部(YEG)が次々と設立され、2010年代半ばまでに全国の約9割の商工会議所に青年部が置かれるようになりました (YEG27年度調査 OB会頭104人 総会員数3万人突破 |日商 Assist Biz)。この組織網の拡大に伴い、青年部員数も自然と増加してきました。また、YEGは「次代の地域経済を担う後継者の研鑽と交流の場」として位置付けられ (歴史・沿革 – 日本商工会議所青年部(日本YEG)公式サイト)、地域の若手経営者ネットワークとしての価値があります。地元商工会議所の支援の下で研修会・全国大会・ビジネス交流など様々な活動を行っており、これが若手経営者にとって魅力となっています。「自社の発展と豊かな地域経済社会の構築」を目的に掲げるYEGは、地域貢献活動や他地域との交流(ブロック大会、全国大会)を通じて会員の視野拡大や人脈形成に寄与します。そのため地元で事業を継ぐ後継者層や、若手起業家にとって有益なコミュニティとして機能し、安定的な加入者を得てきました。さらに、日本YEGという全国組織があることで、単会(各地青年部)同士の情報交換やベストプラクティス共有も行われ、所属メリットが大きい点も加入促進要因です。
減少要因・課題: 一方で近年の微減傾向には、会員の年齢制限と世代交代問題が影響しています。YEGは45歳で原則卒業となるため、常に一定数の退会(卒業)が発生し、新規入会で補填しなければ会員数は維持できません。少子高齢化に伴い地方ほど後継者不足・若手経営者人口の減少が起きており、新陳代謝が追いつかない支部も出ています。また組織のマンネリ化も課題です。設立から40年経ち組織文化が固定化する中で、若年層にとって魅力が薄れる恐れがあります。実際、「青年部」という名称ながら平均年齢が上昇し活力低下を指摘する声や、「地域の青年経済団体として青年会議所(JC)など他団体との差別化」に悩む声もあります。さらにコロナ禍では交流行事の中止やオンライン化で結束力維持が難しく、新規勧誘活動も停滞しました。その結果、2019年比で数%の会員減となった経緯があります (日本YEG 415カ所3万2552人に 21年度青年部の現状 |日商 Assist Biz)。今後は入会促進策の強化(例えば会員拡大キャンペーンやメリット訴求)や、卒業後のOB人脈の活用などで現役部員への魅力付加が求められるでしょう。
競争環境・ビジネスモデルの影響: YEGの競合環境としては、他の青年経済人団体との関係が挙げられます。典型的なのは各地の「青年会議所(JC)」で、戦後から活動する歴史ある青年経済団体です。実際、都市部では商工会議所が青年部設置に消極的だった背景に「既にJCが存在する」ことがありました (歴史・沿革 – 日本商工会議所青年部(日本YEG)公式サイト)。現在ではYEGとJCは並立し、メンバーが重複することもありますが、JCは主にまちづくりや社会貢献色が強く、YEGは商工会議所支援の下で地域企業振興に重きを置くという役割の違いがあります。このため競合というより補完的に共存している面もあります。またYEGは商工会議所という公的経済団体の一部門であり、ビジネスモデル的には会議所の年会費の一部で運営されたり独自会費で活動したりしています。営利ではなく会員サービス・地域貢献が目的の団体のため、ネットワーキング自体を商品化しているBNIなどとは性質が異なります。ただし時代の変化(IT化や若者の価値観変化)はYEGにも影響します。例えばオンライン交流への対応や、SDGsなど新たなテーマへの取り組みが求められ、実際に日本YEGでも「日本版SDGsの推進」に積極的に取り組み始めています (〖6月23日(金)放送〗ラジオ番組 青木仁志のトップリーダーと語る「成功の技術」、日本商工会議所青年部会長の木村麻子さんがゲストで登場! | アチーブメント株式会社のプレスリリース)。今後はデジタルネイティブ世代へのアプローチ(SNS発信の強化、オンラインコンテンツの充実)や、多様な業種・背景の若手が参加しやすい環境づくりが鍵となるでしょう。組織ビジョンとしては中期ビジョン(2023-2027)で「変革の道導となる」と掲げており (中期ビジョン – 日本商工会議所青年部(日本YEG)公式サイト)、従来の延長線上だけでなく新しい価値提供を模索することで、会員減少に歯止めをかけ成長を持続させる意向が見られます。
BNIジャパンの動向と要因
概要と会員数推移: BNI(Business Network International)は世界最大級の異業種交流リファーラル組織で、日本では2006年に展開が始まりました。BNIジャパンはフランチャイズ方式で各地域(リージョン)にチャプターを設立し、週次の定例会で紹介(リファーラル)を交換するビジネス交流を提供しています。日本での会員数は急速に拡大し、2015年9月に7,000名を突破 (BNI Japan – 会社概要 | Japanese)、2017年6月に8,000名 (BNI Japan – 会社概要 | Japanese)、2018年に9,000名、2021年5月に1万人、同年12月には早くも1万2000名に達しました (BNI Japan – 会社概要 | Japanese)。特にコロナ禍の2020~21年にかけて、対面からオンラインへの迅速な移行 (BNI Japan – 会社概要 | Japanese)により停滞するどころか会員数が飛躍的に増加しています。2021年だけで約2500名の純増があり (国内メンバー数が12000名を突破 │ BNI JAPAN NEWS〖世界最大級のビジネス・リファーラル組織BNIジャパンのニュース〗)、現在(2023年時点)では会員数約1万2921名(2023年7月末現在) (1,000名の子供たちが夢をカタチに BNIが子供たちを対象にしたワークショップを実施 | JBNインターナショナル株式会社公式サイト)と報告されています。国内のチャプター数も295(2022年末時点)からさらに増え、2023年時点で360前後のチャプターが全国1都1道2府20県に存在します (国内メンバー数が12000名を突破 │ BNI JAPAN NEWS〖世界最大級のビジネス・リファーラル組織BNIジャパンのニュース〗) (BNI Japan)。まだ未進出の県もあり、BNIは日本全国で拡大途上にあります。将来予測(2035年): BNIジャパンは過去10年間で顕著な成長を遂げており、この傾向が続けば2035年には2万名以上の会員規模に達する可能性があります。特に現在未開拓の地域(例:東北・北陸の一部や四国など)への展開や、主要都市でのチャプター増設が進めば、1チャプター平均40名×500チャプター=2万名といった水準も射程に入ります。ただし、市場飽和や競合出現により成長率が鈍化すれば、1.5万~2万名程度で落ち着くシナリオも考えられます。
成長要因: BNIの成功要因は、明確なルールと成果志向のビジネスモデルです。週1回定例の早朝会合への出席義務やチャプター内での職業カテゴリ独占制(一業種一人)、紹介件数の記録管理など、BNIは非常にシステマチックに運営されます。この「ギバーズゲイン(与える者は与えられる)」の理念に基づく仕組みが中小企業・小規模事業者に確実なビジネス機会をもたらすことが実証され、多くの起業家や営業パーソンが参加しました (BNI Japan – 会社概要 | Japanese)。日本上陸当初は欧米型の手法に懐疑もありましたが、紹介による売上創出という実利に直結する点が支持され口コミで広がりました。フランチャイズ戦略による地域展開もうまく機能しました。各地域にエグゼクティブディレクターを置き、地元でチャプター立ち上げを推進する体制で2006年に東京で開始後、次々に大阪・名古屋など都市圏へ拡大し、2010年代後半には地方中核都市にも進出しています (BNI Japan – 会社概要 | Japanese)。2014年から2017年にかけて毎年約1000名規模で増えてきた背景には、全国で次々と新チャプターが誕生したことが挙げられます(2014年11月に6000名、2015年9月7000名、2017年6月8000名…と順調に節目を達成 (BNI Japan – 会社概要 | Japanese))。さらに、コロナ禍で対面ネットワークが停滞する中、BNIはオンライン移行の素早さと全国のネットワークを活かし、「どこにいても参加できるBNI」として逆に新規会員を増やしました (国内メンバー数が12000名を突破 │ BNI JAPAN NEWS〖世界最大級のビジネス・リファーラル組織BNIジャパンのニュース〗)。例えばそれまで未展開だった地域(札幌、仙台、金沢、松本、広島など)にオンラインでチャプター設立→のちにリアル化という手法で2021年だけで56チャプター新設という急拡大を果たしています (国内メンバー数が12000名を突破 │ BNI JAPAN NEWS〖世界最大級のビジネス・リファーラル組織BNIジャパンのニュース〗)。このように着実なROI(投資対効果)への期待と、広がる地域ネットワークがBNI会員増加の原動力です。
減少要因・課題: BNIの潜在的リスクとしては、会員維持のハードルの高さがあります。ルールが厳格であるがゆえに、週1回早朝というスケジュール負担や毎回の紹介成果プレッシャーについていけず退会するケースもあります。またカテゴリ独占制ゆえに定員が限られ、興味があっても参入できない人(枠が埋まっている業種)も出ます。そうした人が他の交流会(例えばニーズマッチ)へ流れる可能性があります。さらにコロナ後の環境変化でリアル交流の価値が改めて問われる中、オンライン上のコミュニティ(LinkedInグループやSNS経由の紹介など)との競合も長期的には考えられます。BNIは有料会員制(年会費+食事代等の負担)であり不況時には経費削減で退会が増える懸念もあります。今のところ日本では堅調ですが、米国本部の方針変更やフランチャイズオーナーの経営によってサービス品質に差が出るリスクもあります。またチャプター数増加に伴い、紹介の質の維持も課題となります。会員が増えすぎたり類似業種が増えると、一人あたり得られる紹介件数やクオリティが下がり不満に繋がりかねません。BNIジャパンでは統計データを公開し透明性を高めていますが、今後は各メンバーへの教育(より質の高いリファーラルの出し方など)に注力しないと成長鈍化に転じる可能性もあります。
競争環境・ビジネスモデルの影響: BNIのビジネスモデルは、有料フランチャイズ型の異業種交流会として特異な存在ですが、日本国内では類似のコンセプトを持つ団体が登場しています。その代表が後述するニーズマッチで、BNIに比べ自由度が高いビジネス交流会として会員を増やしています。BNIとニーズマッチは直接的な競合関係にあり、特に都市部では入会候補者の取り合いになるケースもあります。BNIの強みは世界規模のネットワークと実績であり、国際的な交流機会やブランド信頼があります。一方弱みは前述の参加ハードルの高さです。ニーズマッチなどはその隙間を狙い「もっと気軽に参加できる交流会」として台頭してきました。BNIはこうした競合に対抗するため、組織力を活かした付加価値提供を進めています。例えばJCI(青年会議所)と2020年にグローバルパートナー提携を結ぶなど (BNI Japan – 会社概要 | Japanese)、他ネットワークとの連携で会員に新たなメリットを提供しようとしています。また、BNI自体もオンラインチャプターやハイブリッド例会などフォーマットを柔軟にし始めており、新規層の取り込みを図っています。ビジネスモデルの観点では、BNIは会員拡大が直収入につながるため、今後も営業的に積極展開を続けるでしょう。2035年に向け、残る全都道府県進出や地方都市での定着が見込まれ、競争環境下でも優位を保つには、地域特性に合わせたチャプター運営(例えば地方では月2回開催にする等の工夫)や、デジタルプラットフォーム活用による他組織との差別化が鍵となります。将来的には会員数の多い米国(7万~8万人規模)に次ぐ世界第2位のBNI市場として、日本がさらに存在感を示す可能性もあります (第200回 進化を加速させる – BNI Japan Official Podcast)。
ニーズマッチの動向と要因
概要と会員数推移: ニーズマッチは2014年9月に東京で創設された比較的新しいビジネス交流会です (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ)。デール・カーネギーの「人を動かす」に基づく「貢献・感謝・承認」を行動指針とし、「その場ですぐにあなたのビジネスが売れる」を掲げています (ニーズマッチのご紹介)。具体的には月1回程度の交流会(各支部で開催)で参加者同士がビジネスマッチングを行う仕組みです。BNIと異なり出席義務やカテゴリ独占の制約が緩く、他支部への自由な訪問も可能なフリーな風土が特徴です (ニーズマッチの歩き方:交流会で成果が出る人、出ない人)。会員数の推移: 創設当初は東京の数支部から始まり、2015年時点では支部数数カ所・会員も数十~数百名規模の小さな組織でした(公式には2015年8月時点で延べ参加者数3000名を記録 (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ)とあるものの、これは参加延人数であり実会員数ではありません)。その後口コミやSNSを通じて広がり、支部は首都圏中心に増加しました。2021年9月には創設7周年を迎え、この時点で公式に「会員数1,026名」と発表されています (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ)。つまり約7年間で会員数1000名規模に成長したことになります。その後、コロナ禍を契機にオンライン対応(ネット支部の設置)を加速させ、地理的な制約なく全国展開が進みました。2024年1月現在では全国16都道府県に161支部(うちオンライン専用「ネット支部」が72)を擁するまでになっています (ビジネス交流会 ニーズマッチ 公式ホームページ)。各支部の会員数は公表されていませんが、会員番号の割り振りは4000番台~6000番台に及んでいるとの情報もあり ( ニーズマッチ活用&質向上委員会参加申し込み – ニーズモール)、延べ登録会員は数千人規模に達していると推測されます。ただし在籍会員(アクティブ会員)が何名かは不透明で、2021年時点の1026名から考えると**現在(2025年頃)でおそらく数千名(1~2千程度)のアクティブ会員がいると見られます。将来予測(2035年): ニーズマッチはビジネスモデル上、BNIに比べて参入障壁が低く今後も地方含め拡大の余地があります。既にネット支部を活用して全国から参加しやすい仕組みを持っているため、2035年までに会員数数千名(3000~5000名規模)**へ成長する可能性があります。うまくニーズに応えれば1万人規模も夢ではありませんが、一方で緩やかな組織ゆえの離脱率も高いと見られるため、着実な定着路線で進んだ場合この程度の規模になると予想されます。
成長要因: ニーズマッチの台頭は、BNIの代替・補完ニーズをうまく捉えた点にあります。BNIが成果重視・高負担であるのに対し、ニーズマッチは「ゆるやかなつながり」を志向し、参加のしやすさを売りにしています。例えば「毎月出席しなければならない」「他支部に行ってはならない」といった縛りがほぼなく自由であること (ニーズマッチの歩き方:交流会で成果が出る人、出ない人)、3ヶ月お試し入会制度があること (ビジネス交流会 ニーズマッチ 公式ホームページ)など、新規が入りやすく継続しやすい工夫があります。また、会員自身が新支部を立ち上げることも奨励されており (ビジネス交流会 ニーズマッチ 公式ホームページ)、情熱ある会員が主体的に地域展開できるモデルです。この結果、トップダウンよりボトムアップで支部数が増えてきました。特にコロナ禍ではオンライン支部の設置により全国どこからでも参加可能となり、一気に支部網が全国規模に広がりました。首都圏以外では有志がZoom上でネット支部を作り、そこからリアル支部設立に繋げるケースもあります。こうした柔軟性の高さが、2020~2023年にかけての拡大要因です。また「その場ですぐに売れる」というコンセプトどおり、各交流会で具体的な商談や契約が生まれる即効性を重視している点も支持されています。ニーズマッチではテーブルごとに自社PRとニーズ発表を行い、その場でマッチング(名刺交換・商談)するスタイルをとります (ニーズマッチのご紹介)。これはBNIのような厳格な紹介プロセスより即時性があり、中には初参加で顧客獲得に至る例もあるようです。低コスト・低プレッシャーで成果につなげたい個人事業主や副業ビジネス従事者などにとって、ニーズマッチは好都合な場となり得ます。このように、BNIには参加できない/しない層の受け皿となったことが成長の原動力です。さらに、運営母体(株式会社ニーズマッチ)が一部上場企業出身者らにより設立されるなどビジネス的な視点も持ち合わせ、メディア露出(日本経済新聞や地方紙に紹介記事掲載 (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ))や金融機関との連携(信用金庫の会議室で支部開催 (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ))など、着実に信頼性を築いてきた点も拡大を後押ししました。
減少要因・課題: ニーズマッチの課題は、会員定着率と収益基盤にあります。自由である反面、会員のコミットメントが低くなりがちで、交流会に来なくなってフェードアウトするメンバーも多いと考えられます。実際、累計の登録会員番号は6000を超えていてもアクティブ会員が2021年時点で1000人程度ということは、かなりの割合が離脱・休眠している可能性があります。ゆるい組織ゆえに参加頻度が低下すると関係性も浅くなり、結果として「思ったよりビジネスにつながらない」と感じて離れる人もいるでしょう。BNIのように強制力がないため成果もメンバー任せになり、支部によって盛り上がりに差が出ることも懸念されます。また、ネット支部中心に急拡大したことで組織運営の統制も課題です。ボランタリーな運営陣(本部役員や各支部役員)の熱意に頼る部分が大きく、一定のクオリティを維持しないと「ただの名刺交換会」となり価値が薄れるリスクがあります。さらにビジネスモデル的に年会費や参加費での収入はBNIほど高くなく(お試し無料期間もある)、持続的な運営資金確保もチャレンジです。2022年末に株式会社ニーズマッチを新規設立し、運営を創業者のコンサル会社から移管したことは (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ)、組織運営を強化する動きと見られますが、収益源を増やす(例えば有料のビジネスマッチング機能やスポンサー導入)なども検討課題でしょう。また、会員同士のマッチング成果が短期志向に偏りすぎると、一部に投資勧誘や保険営業の場になってしまう懸念もあります。実際、ニーズマッチでは特定の金融商品の勧誘は禁止項目になるなどルール整備も進めています (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ)。このように質の維持と量の拡大を両立させることが今後の課題です。
競争環境・ビジネスモデルの影響: ニーズマッチは明確にBNIという先行モデルを意識して生まれており、競争環境もBNIとの比較で語られます。BNIの会員がニーズマッチに移る、あるいは両方参加するケースもあります。例えばBNIでは自分の業種カテゴリーが埋まっていて入れない人がニーズマッチで活動する、といった補完関係が既に生まれています。逆に、ニーズマッチでビジネス交流の手応えを掴んだ人がより本格的なBNIにステップアップする例もあるかもしれません。このように両者は日本のリファーラルマーケティング市場を二分しつつ、棲み分けも進んでいくでしょう。ビジネスモデル的には、ニーズマッチは運営会社によるサービス提供ですが、ボランティア色も強いハイブリッドです。全国統一の有料会員制サービスとしては規模が小さく収益性に課題があるため、今後有料オプションサービスや他事業展開でビジネスモデルを強化する可能性があります。また競合としては、他にも地域発のゆるやかな異業種交流会(任意団体やオンラインコミュニティ)が生まれる可能性があります。例えばFacebookグループを使った無料の紹介コミュニティなど、ニーズマッチよりさらにカジュアルな形態も増えれば、そちらに流れる人も出るでしょう。そうした中でニーズマッチが持続成長するには、独自の付加価値が重要です。例えばニーズマッチ独自のECサイト「ニーズモール」の展開や ( ニーズマッチ活用&質向上委員会参加申し込み – ニーズモール)、会員向け研修(活用&質向上委員会など)の開催によるスキルアップ支援など、単なる交流会以上のメリット提供を進めています。これにより会員の質と満足度を高め、緩い組織でも抜けにくくする工夫を凝らしています。総じて、ニーズマッチは時代の「つながりニーズ」に適合したモデルであり、今後もビジネスモデルのブラッシュアップ次第で十分成長が見込まれますが、BNIという強力な競合と如何に差別化し共存していくかが鍵となるでしょう。
まとめ
中小企業家同友会、日本商工会議所青年部(日本YEG)、BNIジャパン、ニーズマッチの4団体は、それぞれ対象とする会員層や提供価値は異なりますが、いずれも中小企業・起業家のネットワークとして発展してきました。会員数の推移を見ると、同友会は着実な組織拡大で約50万人規模を目指す段階にあり、YEGは全国カバーを達成して横ばい圏、BNIは民間主導で急成長、ニーズマッチも草の根的に台頭中という対照的な状況です。それぞれの成長要因として、同友会は理念と学びの場の提供、YEGは地域後継者ネットワークとしての役割、BNIは成果志向の明確な仕組み、ニーズマッチは柔軟で参加しやすい場作りが功を奏していました。一方、減少要因や課題として、同友会は若手取り込み、YEGは世代交代、BNIは高負担ゆえの離脱、ニーズマッチは定着率向上と収益基盤強化といった点が浮き彫りです。
競争環境とビジネスモデルの変化にも各団体は直面しています。同友会とYEGは非営利型の経営者団体ゆえ直接的な競争よりも社会環境(経営者数の減少など)の影響を受けますが、魅力ある活動を維持し続けないと会員減少の波が来る可能性があります。BNIとニーズマッチは類似領域で競合関係にあり、双方が切磋琢磨することで日本のビジネス交流市場を拡大しています。デジタル化やポストコロナの新常態に適応する動きも重要で、既に4団体ともオンライン活用や組織改革に乗り出しています。例えばBNIとニーズマッチはオンラインチャプター導入、同友会もオンライン例会やウェブでの会員名簿共有開始 (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ)など変革を行いました。
今後2035年に向けて、各団体が成長を続けるには、それぞれの強みを伸ばし弱みを補う戦略が欠かせません。具体的には、中小企業家同友会は若手経営者や後継者へのアプローチを強め地域に根差した経営支援機能を充実させること、日本YEGは時代に即した活動テーマで魅力を維持しつつ他団体と連携して地域経済へのインパクトを高めること、BNIジャパンは品質管理とサービス拡張で会員ROIを維持・向上させながら全国展開を完成させること、ニーズマッチはコミュニティの質醸成と収益モデル安定化で長期的に参加者がメリットを享受できる場にすることが求められます。それぞれの団体がこうした課題に対応できれば、2035年においても会員数は堅調に推移し、ひいては日本全体の中小企業ネットワークが層の厚みを増すことになるでしょう。
参考資料:
- 中小企業家同友会全国協議会「全国では過去最高の4万5556名に」(2016年4月) (静岡同友会が1000名会員達成~企業と同友会の更なる発展を – 中小企業家同友会全国協議会); 「2014年10月時点 会員数43,571名」 (); 「8年間連続増で現在約4万6000名」(2017年6月) (連載第1回〖2019年5万名達成を〗 地域の隅々に同友会理念を広げよう – 中小企業家同友会全国協議会); 「2023年11月現在 会員数47,453名(前年比+1000名)」 (知られていない中小企業の真相と中小企業家同友会); ゴールドオンライン記事 (4万5000人超…なぜこの経営者団体は会員が増え続けるのか | ゴールドオンライン) (4万5000人超…なぜこの経営者団体は会員が増え続けるのか | ゴールドオンライン) 他.
- 日本商工会議所青年部(日本YEG)関連調査(日商Assist Biz記事) (YEG27年度調査 OB会頭104人 総会員数3万人突破 |日商 Assist Biz) (日本YEG 415カ所3万2552人に 21年度青年部の現状 |日商 Assist Biz); PR Timesプレスリリース (〖6月23日(金)放送〗ラジオ番組 青木仁志のトップリーダーと語る「成功の技術」、日本商工会議所青年部会長の木村麻子さんがゲストで登場! | アチーブメント株式会社のプレスリリース); 日本YEG 30周年サイト (はじめに|日本商工会議所青年部 30周年記念サイト) 他.
- BNIジャパン公式サイト「沿革」(BNI Japan会社概要) (BNI Japan – 会社概要 | Japanese) (BNI Japan – 会社概要 | Japanese); BNIニュースリリース (国内メンバー数が12000名を突破 │ BNI JAPAN NEWS〖世界最大級のビジネス・リファーラル組織BNIジャパンのニュース〗) (国内メンバー数が12000名を突破 │ BNI JAPAN NEWS〖世界最大級のビジネス・リファーラル組織BNIジャパンのニュース〗); JBN公式サイト記事 (1,000名の子供たちが夢をカタチに BNIが子供たちを対象にしたワークショップを実施 | JBNインターナショナル株式会社公式サイト); PR Times記事 (BNI 姫路 | Japanese | BNI 姫路) 他.
- ニーズマッチ公式サイト「沿革・ニュース」 (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ); ニーズマッチ公式HP全支部一覧 (ビジネス交流会 ニーズマッチ 公式ホームページ); ニーズマッチ紹介記事(日本経済新聞 等) (沿革・ニュース | ビジネス交流会 ニーズマッチ); ニーズマッチ参加者ブログ (ニーズマッチの歩き方:交流会で成果が出る人、出ない人) 他.
以下、GEMINI 1.5 Deep RESEARCH のデータ
日本の主要な経営者団体の会員数推移分析
はじめに
本稿では、中小企業家同友会を含む日本の主要な経営者団体である、中小企業家同友会、日本商工会議所、経済同友会の会員数推移について分析を行います。
具体的には、以下の観点から分析を進めます。
- 各団体の会員数の推移を、2015年、現在、2035年と比較する。
- 各団体の会員数の推移の要因を、各団体の特徴(設立目的、会員資格、活動内容など)から分析する。
- 中小企業家同友会の会員数推移を、他の主要な経営者団体と比較し、その要因を分析する。
- 各団体の会員数推移を、経済状況、社会情勢、政策動向などと関連付けて分析する。
- 各団体の会員数推移に関する将来予測や展望を、専門家の意見や調査データなどを参考に分析する。
- 上記の分析結果を踏まえ、中小企業家同友会が2035年に向かってどのような会員数になるのか、具体的な数値を予測する。
各団体の概要
中小企業家同友会
中小企業家同友会は、中小企業経営者による自主的な学びと交流を通じて、企業の発展と地域社会への貢献を目指す団体です。1 会員は、企業規模や業種を問わず、中小企業の経営者であれば誰でも加入することができます。 (※会員資格や活動内容に関する詳細な情報は、提供された情報源からは確認できませんでした。)1 定期的な勉強会や交流会、視察研修などを開催し、経営者同士が学び合い、共に成長できる場を提供しています。
日本商工会議所
日本商工会議所は、1922年に設立された、日本経済の発展を目的とする地域総合経済団体です。2 全国515の商工会議所を会員としています。2 中小企業の活性化と地域経済の振興に力を入れています。2 主な活動内容は、政策提言、調査・研究、中小企業の海外展開支援などです。2 地域経済の振興という観点から、地域に根ざした中小企業の活動を支援することに重点を置いています。(※会員資格に関する情報は提供された情報源からは確認できませんでした。)2
経済同友会
経済同友会は、1946年に設立された、企業経営者による経済団体です。3 日本経済の再建と国民生活の向上に貢献することを目的としています。3 企業経営者が個人として参加し、幅広い視野から国内外の諸問題について考え、政策提言を行うことを特色としています。3 会員は、大企業の経営者や役員が中心となっています。3 主な活動内容は、社会・経済問題の解決策の提言、国際的な経済交流、政策提言活動などです。3 グローバルな視点から、日本経済全体の発展に貢献することに力を入れています。
会員数推移の分析
| 団体名 | 2015年 | 現在(2025年2月) | 2035年(予測) |
|---|---|---|---|
| 中小企業家同友会 | データなし | データなし | データなし |
| 日本商工会議所 | データなし | データなし | データなし |
| 経済同友会 | データなし | 1,611名 3 | データなし |
残念ながら、提供された情報源からは、中小企業家同友会と日本商工会議所の会員数の推移に関する具体的なデータを得ることができませんでした。経済同友会については、現在の会員数は1,611名であることがわかりました。3 2015年のデータや2035年の予測値は入手できませんでした。
入手できた情報から、経済同友会は会員数を維持もしくは微増させている可能性があります。これは、大企業を中心とした会員構成と、グローバルな視点での政策提言活動が、経済のグローバル化や社会課題の複雑化といった状況において、経営者にとって魅力的であるためと考えられます。
各団体の会員数推移の要因分析
各団体の会員数の推移は、それぞれの団体の特徴や活動内容、そして経済状況、社会情勢、政策動向などと密接に関連していると考えられます。
中小企業家同友会
中小企業家同友会は、中小企業経営者同士の学び合いと交流を重視しており、会員数は、中小企業の経営状況や、経営者自身の学習意欲、人脈形成ニーズなどに影響を受けると考えられます。
- 経済状況の影響: 好景気時には、企業業績が向上し、経営者の自信や将来への展望が明るくなるため、学習意欲や人脈形成ニーズが高まり、会員数が増加する傾向が見られると考えられます。一方、不況時には、経営者は事業の維持に注力せざるを得なくなり、学習や交流への投資意欲が減退し、会員数が減少する可能性があります。
- 社会情勢の影響: 近年、働き方改革やダイバーシティ&インクルージョンなど、企業を取り巻く社会情勢が大きく変化しています。中小企業家同友会では、これらの社会変化に対応するための情報提供や研修などを実施することで、会員数の増加に繋げている可能性があります。
- 政策動向の影響: 中小企業支援政策の充実度も、会員数に影響を与えると考えられます。例えば、政府が中小企業の経営力向上のための補助金制度を拡充した場合、中小企業家同友会への加入を検討する経営者が増える可能性があります。
日本商工会議所
日本商工会議所は、地域経済の振興を目的としており、会員数は、地域経済の活性度や、中小企業の景況感、政策支援の充実度などに影響を受けると考えられます。
- 地域経済の活性度: 地域経済が活性化し、企業の業績が好調な時は、商工会議所の活動への期待感も高まり、会員数が増加する傾向があります。逆に、地域経済が低迷している時は、会員数の伸び悩みや減少が起こる可能性があります。
- 政策支援: 中小企業向けの政策支援の充実も、会員数に影響を与えると考えられます。例えば、地域活性化のための補助金制度や融資制度が充実すれば、商工会議所への加入メリットが高まり、会員数が増加する可能性があります。
- 中小企業の景況感: 中小企業の景況感が悪化すると、事業の維持・発展に不安を感じ、商工会議所への加入を控える企業が増える可能性があります。
経済同友会
経済同友会は、政策提言や国際交流を重視しており、会員数は、経済のグローバル化や、社会課題の複雑化、政策決定への影響力などに関心を持つ企業経営者の数に影響を受けると考えられます。
- 経済のグローバル化: 経済のグローバル化が加速する中で、海外進出や国際的なビジネスに関心を持つ企業経営者が増え、経済同友会への加入を検討する企業が増加する可能性があります。
- 社会課題の複雑化: 環境問題、少子高齢化、格差問題など、企業を取り巻く社会課題はますます複雑化しています。これらの課題解決に貢献したいと考える経営者にとって、政策提言や社会貢献活動に力を入れる経済同友会は魅力的な存在となり、会員数の増加に繋がる可能性があります。
- 政策決定への影響力: 経済同友会は、政府や政党に対して積極的に政策提言を行っており、政策決定に一定の影響力を持っていると考えられます。政策への関心が高い経営者や、自社の事業に有利な政策を推進したいと考える経営者にとって、経済同友会は魅力的な団体となり、会員数が増加する可能性があります。
経済状況、社会情勢、政策動向と会員数推移の関係
上記で述べたように、各団体の会員数推移は、経済状況、社会情勢、政策動向と密接に関連しています。
- 経済状況: 景気動向は、企業の業績に直接影響を与えるため、各団体の会員数推移に大きな影響を与えます。好景気時には会員数が増加傾向にあり、不況時には減少傾向にあります。
- 社会情勢: 少子高齢化、グローバル化、情報化など、社会情勢の変化は、企業経営に大きな影響を与えます。各団体は、これらの変化に対応するための情報提供や支援活動を行うことで、会員数の維持・増加を図っています。
- 政策動向: 政府の政策は、企業活動に大きな影響を与えるため、各団体の会員数推移にも影響を与えます。特に、中小企業支援政策や規制緩和政策などは、中小企業家同友会や日本商工会議所の会員数に大きな影響を与えると考えられます。
結論
本稿では、限られた情報源に基づき、中小企業家同友会を含む日本の主要な経営者団体の会員数推移について分析を試みました。会員数の推移に関する具体的なデータは不足していましたが、各団体の概要、活動内容、そして経済状況、社会情勢、政策動向との関連性から、会員数推移の要因について考察しました。
分析の結果、各団体の会員数推移は、それぞれの団体の特徴や活動内容、そして経済状況、社会情勢、政策動向などと密接に関連していることがわかりました。
- 中小企業家同友会は、中小企業経営者同士の学び合いと交流を重視しており、会員数は中小企業の経営状況や経営者の学習意欲、人脈形成ニーズに影響を受けると考えられます。
- 日本商工会議所は、地域経済の振興を目的としており、会員数は地域経済の活性度や中小企業の景況感、政策支援の充実度に影響を受けると考えられます。
- 経済同友会は、政策提言や国際交流を重視しており、会員数は経済のグローバル化や社会課題の複雑化、政策決定への影響力に関心を持つ企業経営者の数に影響を受けると考えられます。
これらの分析から、各団体は、それぞれ異なるニーズを持つ企業経営者に対して、独自の価値を提供することで会員を獲得し、維持していると考えられます。
今後、日本経済がどのように変化していくか、そして各団体がどのような役割を果たしていくのか、注目していく必要があります。
引用文献
1. 1月 1, 1970にアクセス、 https://www.doyu.jp/about/rinen
2. 日本商工会議所とは, 2月 7, 2025にアクセス、 https://www.jcci.or.jp/about/jcci/
3. 組織概要|経済同友会, 2月 7, 2025にアクセス、 https://www.doyukai.or.jp/about/org.html